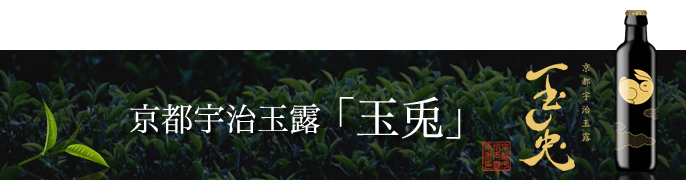- 2025-01-26 (日) 6:00
- お役立ちコラム

日本の伝統的な飲み物であるお茶。
そのお茶の生産には、茶摘みという重要な工程があります。
茶摘みの時期は、お茶の品質や風味に大きく影響するため、お茶好きにとっては気になる情報の一つでしょう。
今回は、茶摘みの時期に関する様々な情報を網羅的にご紹介いたします。
地域や品種、気候といった要素がどのように茶摘みの時期に関わっているのか、そして、新茶を楽しむための方法についても解説します。
茶摘み時期を知るための基礎知識
茶摘みの回数と時期
お茶の収穫は、一般的に一番茶、二番茶、三番茶、秋冬番茶などに分けられます。気温の影響を受けるため、地域やその年の気候によっては、収穫回数が異なる場合があります。
例えば、温暖な地域では年間4回程度の茶摘みが行われる一方、寒冷な地域では2回のみという場合もあります。
また、古くから行われている茶摘みでは、年1回のみ収穫する地域もあるようです。
一番茶は、その年の最初の収穫で、新芽の柔らかく香り高い葉を使用するため、新茶として高い人気を誇ります。
一番茶の収穫時期は地域によって異なり、早くて3月下旬から4月上旬、遅くて5月下旬頃までと幅があります。
二番茶は一番茶の収穫後、約45~50日後に収穫されます。
三番茶は7月下旬から8月上旬にかけて収穫され、カテキンを多く含むことが特徴です。
秋冬番茶は9~10月頃に収穫され、地域によっては行われない場合もあります。
地域による茶摘み時期の違い
日本の茶産地は南北に広がっており、地域によって気候条件が大きく異なります。そのため、茶摘みの時期も地域差が生じます。
例えば、温暖な九州地方では3月下旬頃から茶摘みが始まり、関東地方では5月頃、北海道ではさらに遅くなります。
「新茶前線」という言葉があるように、茶摘みの適期は日本列島を北上していく様子が見て取れます。
品種による茶摘み時期の違い
お茶の品種によっても、生育速度や摘み取り適期が異なります。早生品種は生育が早く、比較的早い時期に収穫できます。
一方、晩生品種は生育が遅いため、収穫時期も遅くなります。
品種によって最適な収穫時期を把握することが、高品質なお茶を作る上で重要となります。
気候と茶摘み時期の関係
茶摘みの時期は、気温や日照時間などの気候条件に大きく影響を受けます。適度な気温と日照時間が確保され、生育が良好な状態であることが、品質の良いお茶を収穫する上で重要となります。
霜の被害に注意が必要な時期もあり、気候の状況を常に把握することが茶農家にとって不可欠です。
特に八十八夜(立春から数えて88日目)は、古くから茶摘みや農作業の目安とされ、この頃には霜の心配が少なくなると言われています。

茶摘み時期と新茶を楽しむ方法
新茶の特徴と選び方
新茶は、その年の最初の収穫でできたお茶で、一番茶のことを指します。新茶の特徴は、なんといってもその鮮やかな緑色と、柔らかく繊細な風味です。
選び方としては、葉の鮮やかさ、香り、そして産地や品種なども考慮すると良いでしょう。
新茶のおいしい入れ方
新茶のおいしい入れ方は、茶葉の種類や好みによりますが、一般的には、熱湯ではなく、やや低めの温度のお湯で抽出するのがおすすめです。急須を使う場合は、茶葉が十分に開くように、少し時間をかけて蒸らすことがポイントです。
新茶を使ったおすすめレシピ
新茶は、そのまま飲むだけでなく、様々な料理にも活用できます。例えば、新茶を使ったゼリーや、新茶風味のクッキーなど、お茶の風味を生かしたオリジナルレシピを楽しむことができます。
茶摘み体験イベント情報
近年、茶摘み体験ができるイベントが各地で開催されています。茶畑で実際に茶摘みを体験することで、お茶作りの工程をより深く理解し、お茶への愛着がさらに深まるでしょう。
各地の観光情報サイトなどで、開催情報をチェックしてみてください。

まとめ
今回は、茶摘みの時期に関する様々な情報を網羅的にご紹介しました。地域や品種、気候といった要素が、茶摘みの時期にどのように影響を与えているのかを理解することで、よりお茶の味わいを楽しむことができるでしょう。
新茶の選び方や入れ方、そして茶摘み体験イベントの情報もご紹介しましたので、ぜひ、この記事を参考に、お茶の豊かな世界に触れてみてください。
新茶の季節は、一年の中でも特に魅力的な時期です。
様々な新茶を試したり、茶摘み体験に参加したりすることで、お茶の楽しみ方がさらに広がることでしょう。
お茶の風味や品質は、茶摘みの時期や方法、そして茶葉の生育環境など、様々な要素が複雑に絡み合って生まれます。
この記事が、お茶をより深く理解し、楽しむための一助となれば幸いです。